この本を読む前と後では子育ての考え方が変わります。
少なくとも私にとってはそのくらい衝撃的で、心から納得させられる一冊でした。
本の紹介文
2020年4月に発売された
島村華子さんの「自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方」
表紙にもありますが
著者はモンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育を知り尽くしたオックスフォード児童発達博士です。
この教育方針は『こども一人ひとり独立した平等たる一市民である』という考え方で、この本の支柱です。
どうやって接するのが子供のためになるんだろう。
本書はこのような悩みを解決してくれる一冊です。
私も子育て真っ最中。
悩むこともたくさんありましたが、この本を読んで考え方のベースが固まり、迷いはだいぶ減りました。
正直もっと早く出会いたかった本です。
前提:【自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方】はこんな方にオススメ
- 子育てでしょっちゅうイライラしてしまう
- 子育てが理想のイメージ通りいかないと思っている
- 子供と良好な関係をいつまでも保ちたい
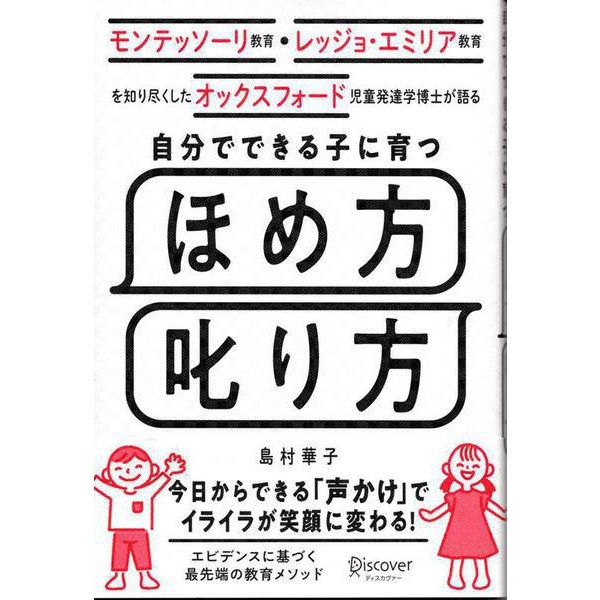
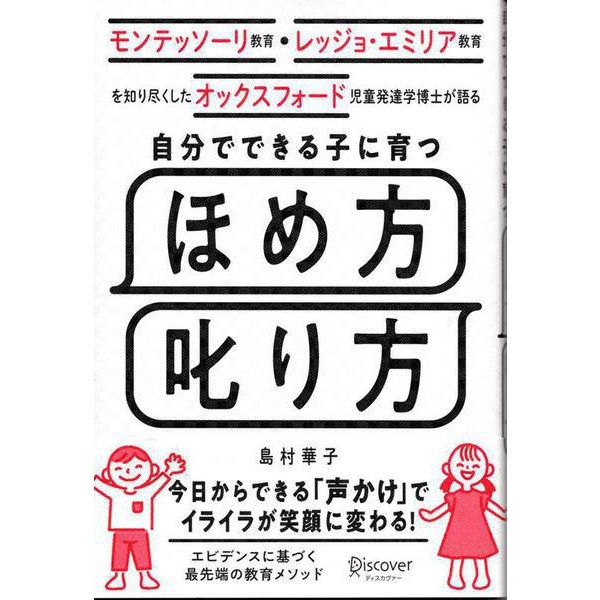
納得:6つの抜粋ポイント
愛情をエサにする接し方を繰り返すと、ほめられたときに愛されていると感じ、逆にそうでないときには愛されていないと感じてしまうのです。
出典:自分でできる子に育つほめ方叱り方 P.20
条件付きの接し方と、無条件の接し方のが子供にどう影響するのかが具体的に書かれています。
もうこの時点で反省しまくりです。。。
子育てにおけるよきリーダーとは、子供に向き合い気持ちに寄り添いながらも、必要な制限を設け、子どもに道しるべを示す人を指します。
出典:自分でできる子に育つほめ方叱り方 P.38
親は基本どっしり構えて、任せるところは子供にやらせ、必要な時にちゃんと助けてあげられる必要があるということですね。
子どもをほめるときに大切なのは、能力や性格をたたえるのではなく、取り組んでいる過程での努力や挑戦した姿勢、やり方を工夫した点などに言及し、励ましてあげることです。
出典:自分でできる子に育つほめ方叱り方 P.58
これぜひ意識的に実践してほしいです。
実際、私も行ってのですが、明らかに子供の聴く態度が変わりました。何が良かったのかが分かると子どもはきっと安心するんですね。
まず「ダメ!」と口走る前に、子どもが何をしたかったのか、何を言いたかったのかを理解し、ありのままの子どもを受け入れたうえで手を差し伸べるということです。
出典:自分でできる子に育つほめ方叱り方 P.98
「ダメ!」「違う!」は日常ついつい咄嗟に出てしまいますよね。
もちろんに見の危険の場合には必要ですが、そうでない場合は一度冷静になって子どもに寄り添う気持ちが大切でなんですね。
相手を批判したり否定したりせずに、「私」自身の気もちを中心に、自分自身がどう感じているか、またその理由が何であるかということを伝えながらコミュニケーションをとる方法です。
出典:自分でできる子に育つほめ方叱り方 P.103
ほめたり叱ったりする中で、自分(親)が思っていることを伝えることが大切ということですね。
子どもも親がどう思っているのか知りたいはずですし、伝えることで納得しやすいのではないでしょうか。
アクティブ・リスニングとは、話し手に対して100%の注意を向けて、その人の話を足し算引き算することなく、無条件に聞き入れることです。
出典:自分でできる子に育つほめ方叱り方 P.131
忙しいときなど子どもに話しかけられても「うん・・うん・・」と流し聞きしちゃってることってありませんか?
家族だから成り立つのかもしれませんが、普通に逆の立場で考えたら・・
実践:3つの今日からできること!
・1人の立派な人間として向き合う
・「ダメ!」を必要以上に言わない
・自分の気持ちをちゃんと伝える
まとめ


読み進めていくと、普段からできてないことばかりで正直かなり凹みました。
「過去に戻ってやり直したい・」・・なんて思うことばかり。。
ですが本にも書かれていますが親も一人の人間であって完璧でないのは当たり前です。
失敗はたくさんするだろうし、そこから学ぶこともきっと多いですよね。
子どもだって一人の立派な人間!そんなにやわじゃない。
もちろん子供が幼いころから実践できる方がいいですが
子どもが小学生・中学生でも(例え大人であっても)この本で書かれているコミュニケーションのとり方は非常に大切だと感じます。
今日から意識して取り組めばきっと今以上の良好な関係が築けるはずです。
本書を購入し、あえて少し肩の力を抜いて読んでみてください。
最後までありがとうございました。


